
|
表1 対象者数。
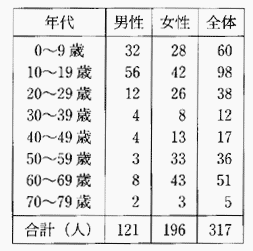
保育園、6〜14歳は小・中学校、15歳以降は、大学および地域のプールやスポーツ施設の利用者およびスポーツ教室(体操、水泳)参加者である。 日時は1995年の夏から秋にかけてである。 2. 方法
a. 記録 8mmビデオカメラを対象から6〜8mの距離 に固定し、立位での上体の屈曲・伸展運動を側方より撮影した。その際、両足を左右に足長程度開いてもよいこと、“できるだけたくさんおこなう”よう指示した。3〜5歳については、伸展時に、検者が背を支えて補助した。また、立位での屈曲ができない幼児については、長座位で上から背をかるく押して行った。0〜1歳の乳児については、保育室の広さに制約があり、3〜5mの距離から撮影した。また、屈曲については、保母の膝に乳児の背を寄り掛からせ、その姿勢から足首を引きよせた。一方、伸展では、仰臥位から保母が乳児の腰を両手で持ち上げ、足や頭が床から離れる直前の形態を計測した。 b. 基準点の設定 側面映像について、正中垂直軸ぞいに耳珠(A)、胸骨上縁水平線の中点(B)、胸骨下水平線の中点(C)、肋骨下水平線の中点(D)、大転子(E)、膝関節の中点(F)、足関節外果点(G)を設定した(図1)。なお、胸骨上縁水平線の点Bは肩峰(aCromion)および上肢学上時には腋窩に、胸骨下はみぞおちに、肋骨下水平線はウエストラ 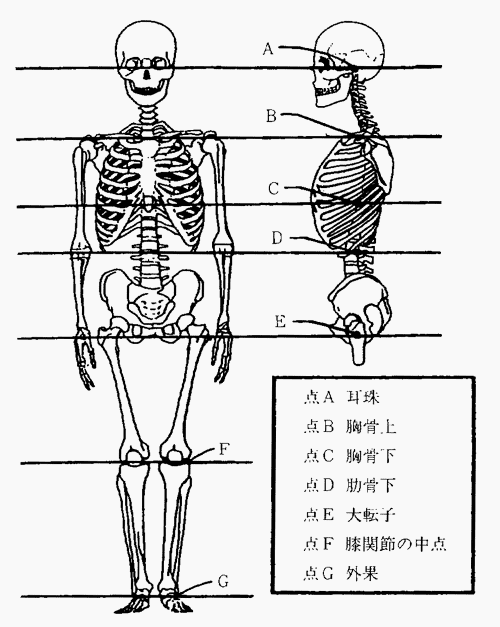
図1 屈曲・伸展の形状分類と角度計測に用いた基準点。
インに近似する。 C. 屈曲・伸展のパターン分類 屈曲・伸展位においては、上記基準点のうち床から最も高くなる点によって『A型』『B型』『C型』『D型』『E型』に分類した。『A型』から『E型』に進むにつれて屈曲・伸展度は大きくなる。 d. 屈曲・伸展角 屈曲・伸展角ともに2種類の計測を行った。『屈曲角I』(図2)では、体幹後面と大腿中軸を通る直線EFの交点をa、肋骨下水平線との交点をbとし、abを結ぶ線とaを通る床との平行線がなす角(f・I)を求めた。そのさい、この2線が重なればO,b点が平行線より下にあれば十、上にあれば一になる。『屈曲角II』(図3)では、点C,D,Eについて、その上下の点とその点を結ぶ直線のなす交点の前面角を求めた。 『伸展角I』では(図4)、立位でのA・Gを結ぶ線分と、伸展時のA・Gを結ぶ線分のなす角(e・I)を求めた。『伸展角II』では、図5にしめすように、点B,C,D,Eについて、その上
前ページ 目次へ 次ページ
|

|